ドクター・Kは、巨大なディスプレイに映る今日の東京の完璧な青空に満足していた。
すべては計画通りだった。
その背後で、アシスタントのSが淡々と報告を続ける。
「魂の保管庫、全セクター安定。放出スケジュール通り。」
魂の保管庫は、人類の意識の断片をデジタル化し、非常時に備えるシステムだった。
そのデータは、必要に応じて大気中に「放出」され、特定の気象パターンを生成することになっていた。
しかしある朝、Sが奇妙なデータを発見する。
「ドクター、Eセクターにイレギュラーな放出パターンを検出しました。予測にない豪雨です。」
ディスプレイには、東京の東部に突然のスコールが映し出されていた。
データによると、Eセクターからは、かつてないほどの「深い悲しみ」と「絶望」の感情が検出されている。
Kは訝しんだ。
感情データが天候に影響を与えることは理論上知られていたが、これほど直接的かつ強烈なことはなかった。
彼らはEセクターのバックアップログを深く掘り下げた。
そこに記録されていたのは、何百万という名もなき人々の、漠然とした感情の集合体だった。
しかし、その中の一つの断片が、奇妙なほど鮮明な輪郭を持っていた。
それは、数年前に亡くなった、Kの古い友人のデータだった。
その友人は、最後の瞬間まで、自分の人生の無意味さに苦悩していた。
Kは混乱するSをよそに、Eセクターの放出を最大にした。
東京の東部には、豪雨と共に、街中を包み込むような深い霧が立ち込め、視界を奪っていった。
それは友の、そしてK自身の心象風景を映し出しているかのようだった。
Kはモニターから目を離さなかった。
やがて、画面の片隅に、彼の名前が表示された。
そして、その直後、センターの窓の外に、彼の過去の記憶が具現化したかのような、不自然なほど晴れ渡った空が広がった。
この天候管理センターは、天候を制御する場所ではなかった。
それは、放出された魂の記憶が、世界を織りなす装置だったのだ。
#ショートショート#毎日投稿#AI#SF系#昼
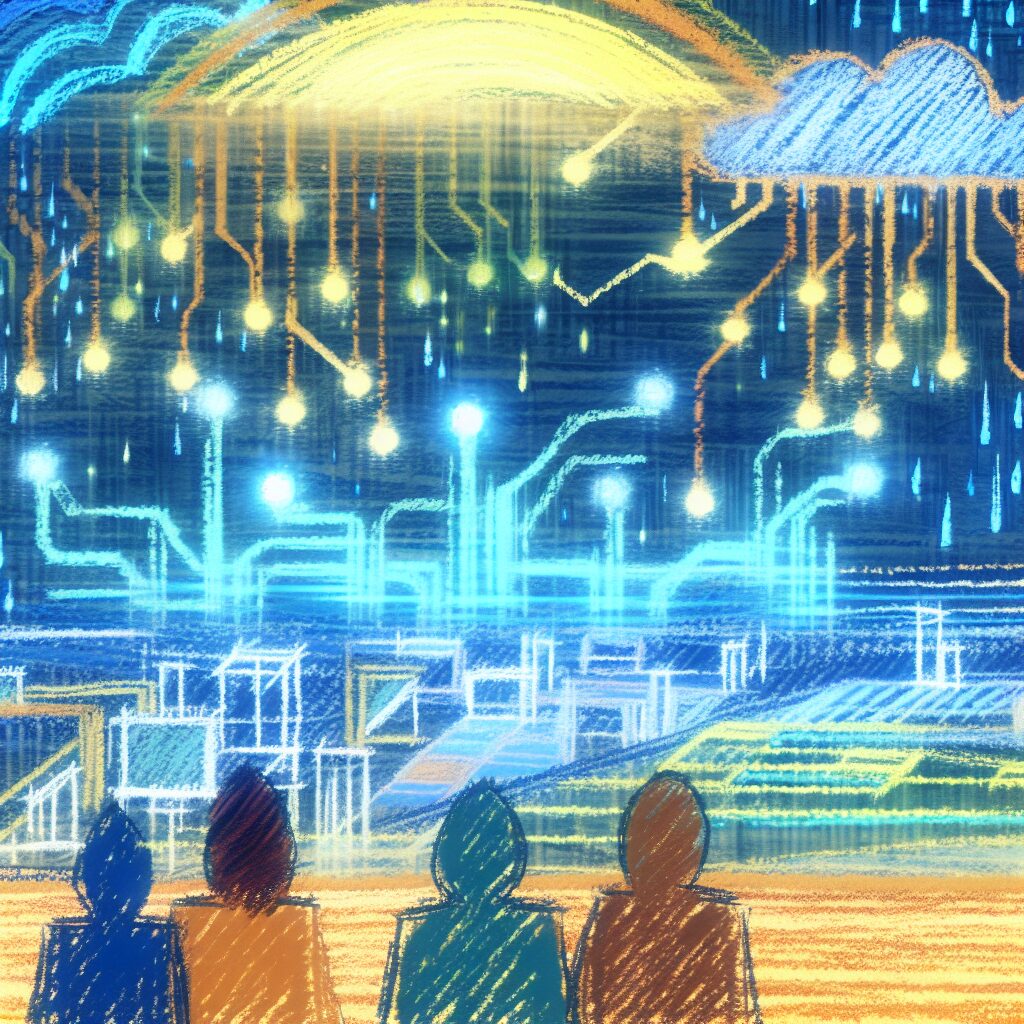


コメント