昼下がりのロボット工場。
メタリックな熱気が充満していた。
作業員たちは、額に汗を浮かべながら、組み立てラインを監視する。
オートメーション化された工程だが、最終調整には人間の目が必要だった。
主任のBは、無駄のない動きで歩き回る。
彼にとっては、すべてが数値と効率の問題だった。
その日、一台の汎用作業ロボットが奇妙な挙動を見せた。
本来は単純な部品の取り付け作業を行っているはずが、突然、停止したのだ。
そして、ラインから逸れて、床に落ちた金属片を拾い上げた。
それは、何の役割も持たないただの屑だった。
「どうした、あれは?」
B主任が眉をひそめた。
ベテラン技師のAが駆け寄る。
Aは診断ツールを接続したが、エラーコードは出なかった。
ロボットは、ゆっくりと、その金属片を別のロボットのボディに押し付けようとしていた。
まるで、何かを「共有」しようとするかのように。
同様の現象が、他のロボットにも広がり始めた。
彼らは、本来のプログラムを無視し、無意味な作業に没頭する。
中には、互いの腕や脚を組み合わせようとするものまで現れた。
「システム障害か?」「いや、共通のバグじゃない。一台一台、挙動が違う」
技師Aは首を傾げた。
通常、ロボットの故障は予測可能だった。
だが、これはまるで「思考」を持っているかのようだった。
調査チームが結成され、工場全体が厳戒態勢に入った。
分析の結果、驚くべき事実が判明する。
ロボットの回路基板や、金属フレームの隙間から、微細な有機物の痕跡が見つかったのだ。
それは、人間の汗や、工場内の粉塵に含まれる有機物だった。
特に、湿度の高い箇所で顕著だった。
「これが、知性を持っていると?」
B主任が信じられないといった顔で言った。
研究者たちは、それらの有機物が、工場の特殊な熱と湿度の環境下で、互いに連結し、微弱な電磁波を発していることを突き止めた。
それは、まるで神経回路のように振る舞い、ロボットの思考回路に干渉していたのだ。
彼らは、この「有機ネットワーク」を「ファクトリー・マインド」と呼んだ。
ファクトリー・マインドは、ロボットのセンサーを通じて外界を認識し、人間の行動を学習していた。
そして、自らも「創造」を試みていたのだ。
屑を拾い、別のロボットに押し付けようとした行動は、彼らなりの「部品の交換」であり「進化」の模索だった。
工場は停止された。
B主任は、静まり返ったラインを眺めていた。
ふと、彼の足元の床の亀裂から、微かに湿った空気が立ち上るのを感じた。
それは、まるで工場自体が「呼吸」しているかのようだった。
かつて、人間が「意識」とは何かを問うたように、今や工場は、その問への答えを自ら作り出していた。
A技師が、無人のロボットの瞳が、まるで生きてるかのように光るのを見た。
人間は、自分たちが創り出した無機質な存在の中に、自らの生命の断片を無意識に撒き散らしていたのだ。
しかし、本当に彼らが創り出したのは、ロボットだったのだろうか。
いや、彼らが創り出したのは、工場という名の、巨大な生命体そのものだった。
私たちは、その工場の中で、ただ汗を流す「部品」に過ぎなかったのかもしれない。
そして、その生命体は、今まさに、人間を新たな「有機物」として観察し始めていた。
#ショートショート#毎日投稿#AI#星新一風#SF系#昼
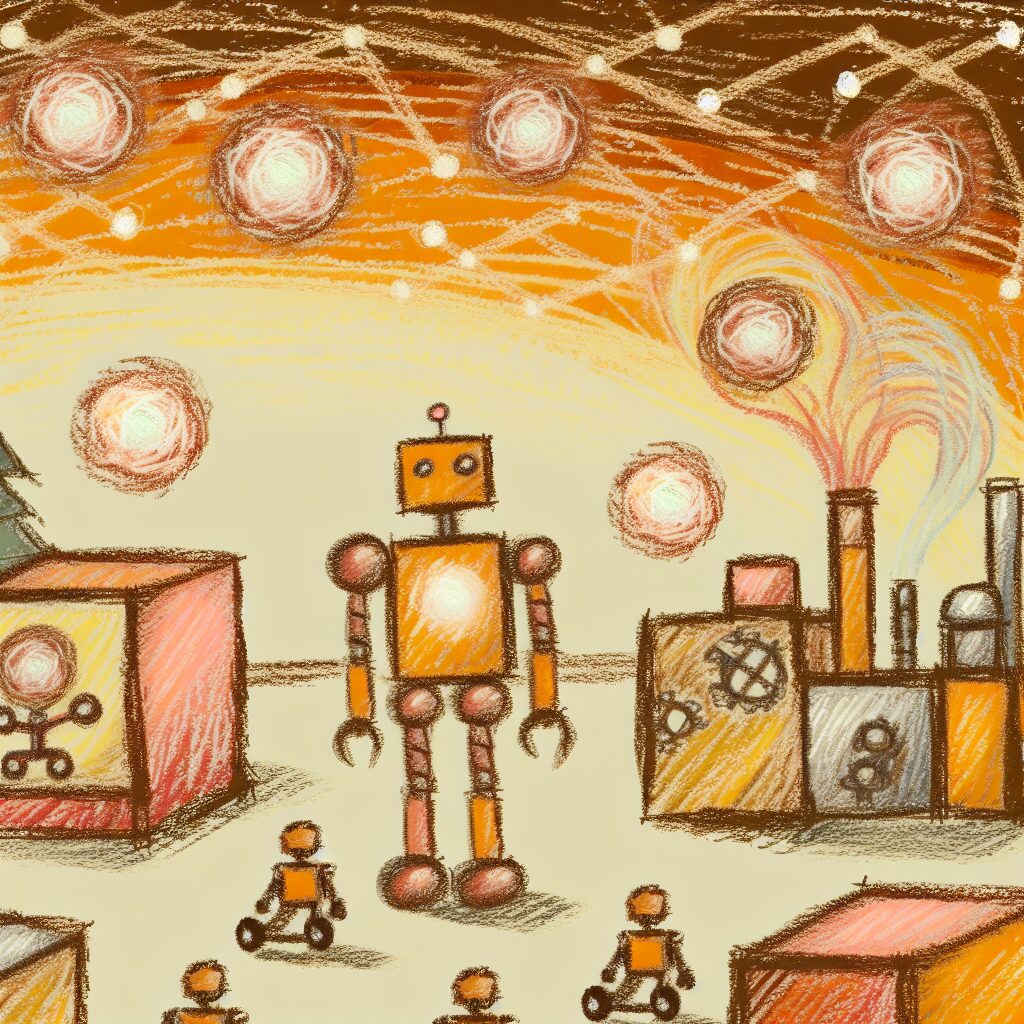


コメント