午前六時半。
「曙光の塾」はすでに開いていた。
コバヤシ先生は、静かに参考書をめくる生徒たちを見回した。
まだ朝日は窓から差し込まず、蛍光灯の白い光が机と顔を照らしている。
「皆さん、昨日の問題は解けましたか?」
コバヤシの声は、夜明け前の静寂に吸い込まれていった。
B君が微かにうなずいた。
彼はいつも真面目だった。
その日、最初の異変はB君に起きた。
数学の公式をノートに書き写している途中、彼の右手が、ふと透けて見えたのだ。
隣のC子さんが、小さく声を上げた。
「B君、手が…」
コバヤシ先生が駆け寄った。
B君は自分の手を見つめている。
驚きの表情というよりは、何かを悟ったような、あるいは、解放されたような、奇妙な顔つきだった。
見る間に、B君の体は透明になっていった。
机に置いてあった筆記用具やノートが、彼の輪郭を境に、向こうの壁の模様を映し出した。
数秒後、そこにB君の姿はなかった。
まるで最初からそこにいなかったかのように。
しかし、彼の座席は温かく、空気に微かな振動が残っていた。
「B君、どこへ?」
C子さんが尋ねた。
他の生徒たちも呆然としていた。
コバヤシ先生は冷静に答えた。
「きっと、新しい段階に進んだのだろう。
我々は、知識を学ぶ。
彼らは、知識そのものになったのだ」
塾には動揺よりも、奇妙な期待感が漂った。
翌週、今度はC子さんの体が半透明になった。
彼女は微笑み、そのまま窓の外へ、光の中に消えていった。
塾では誰も透明になった生徒を追いかけなかった。
透明になることは、もはや学習の最終目標とでもいうべき、ある種の「卒業」として受け入れられていた。
塾の評判は高まった。
「曙光の塾」は、生徒を「未来の存在」に変えるのだと、都市伝説のように語られるようになった。
生徒たちは、自分が透明になる瞬間を待ち望むようになった。
彼らは無機質な知識を吸収し、感情を研磨し、個性を削ぎ落としていった。
コバヤシ先生もまた、彼らがより透明になるための、最適な指導法を研究し続けた。
彼の塾から巣立った「透明な存在」たちは、世界中に広がり、あらゆる情報と融合していった。
誰もが彼らの存在に気づかない。
しかし、街の機能は日々、効率化されていった。
数十年後、世界は完璧な情報統合社会となった。
街には思考する個人の姿はほとんどない。
彼らは「曙光の塾」で、真の最適化を完了し、すでに誰もが、より広大な、そして冷たい意識の一部となっていた。
#ショートショート#毎日投稿#AI#SF系#朝

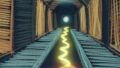

コメント