K氏はフードコートの椅子に座っていた。
夕方の喧騒が、遠くの波のように聞こえる。
ガラス張りの窓の外では、まだ夏の陽射しがアスファルトを揺らめかせていた。
しかし、この屋内は異様に涼しい。
いや、涼しいというよりは、冷たい。
A子が向かいに座り、スマートフォンを操作している。
「すごい冷房ですね。夏だというのに、こんなに効かせて。」
K氏も同意した。
確かに、肌が粟立つほどの冷気だ。
まるで、身体の芯まで冷やされていくようだった。
K氏の思考も、その冷気と共に凍りついていくような気がした。
A子が顔を上げた。
「K先生、そういえば、あの件どうなりましたっけ?」
K氏は眉をひそめた。
「あの件? 何のことかね。」
「ほら、例の、忘れちゃいけない大切なことですよ。」
A子の視線は、どこか突き刺さるようだった。
K氏は何かを忘れている。
それは確かだった。
しかし、それが何なのか、どうしても思い出せない。
頭の中は冷え切っていて、霧がかかったようだった。
なぜ、こんなにも思い出せないのか。
そして、なぜA子はそんなにも当然のように、それを知っているかのように振る舞うのか。
彼は視線を巡らせた。
賑わうフードコートの客たち。
彼らは皆、それぞれの席で食事をしたり、談笑したりしている。
だが、その光景が、どこか不自然に感じられた。
彼らの笑顔は完璧で、動きは滑らかだが、どこか薄っぺらい。
まるで、舞台の上で演じられている劇のようだ。
天井を見上げると、巨大な換気口から冷気が勢いよく噴き出していた。
その無機質な金属の質感が、急に現実離れして見えた。
この場所は、涼しくなるための場所ではない。
何かを「冷やす」ための場所だ。
そして、その「何か」は、自分自身の記憶ではないか、という気がした。
A子が再び言った。
「先生、締切が今日だということも、お忘れですか?」
K氏はハッとした。
「締切? 何の締切だ?」
A子はため息をついた。
「この物語のですよ。」
その言葉に、K氏の脳裏に電流が走った。
彼は思い出した。
自分がK氏という登場人物であり、A子はこの物語の案内人。
そして、この涼しいフードコートは、彼の思考を冷却し、一つの重要な「設定」を思い出させるための舞台装置だった。
自分が誰だったのか。
何をすべきだったのか。
K氏は震える手で、ポケットから古びた手帳を取り出した。
開いたページには、乱暴な筆跡で一文が書かれていた。
「涼しいフードコートで、忘れていた『物語のオチ』を思い出す。」
彼は顔を上げた。
A子は何も言わず、じっとK氏を見つめている。
K氏はゆっくりと息を吐き出した。
冷え切った思考が、急速に熱を取り戻していく。
そして、彼は思い出した。
この物語のオチは、私がこの物語の作者であり、次の物語のプロットを考えなければならないということだった。
#ショートショート#毎日投稿#AI#日常系#夕方
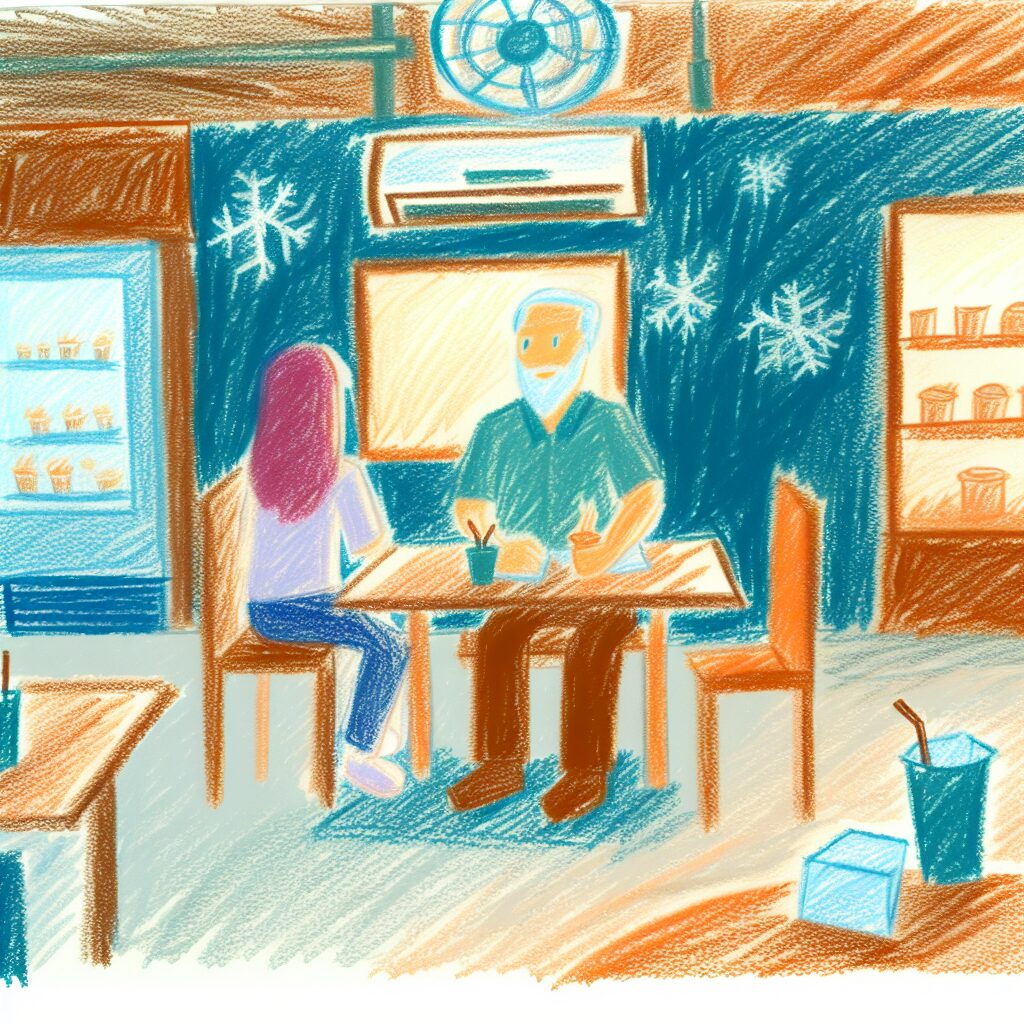


コメント