K氏は、S助手とともに、夕暮れ迫る「静寂荘」の前に立っていた。
かつては賑わった高級ホテルも、今や廃墟と化している。
入り口の看板は朽ち、ガラスは割れて煤けていた。
彼らの任務は、このホテルに残る「消えない痕跡」の調査だった。
不特定の情報源から、奇妙な報告が寄せられていたのだ。
「部屋の埃の中に、真新しい足跡がある」とか、「誰もいないはずのロビーで、カップの音がする」といった類の。
内部は、湿った空気が澱み、埃の匂いが充満していた。
ロビーの豪華なシャンデリアは錆びつき、床には絨毯の繊維が散乱している。
フロントのカウンターは倒れ、電話機は泥にまみれていた。
S助手は懐中電灯を構え、K氏はメモを取りながら進む。
二階の客室フロアは特に荒廃が激しかった。
扉は歪み、壁紙は剥がれ落ちている。
とある部屋に入った時、S助手が小さく声を上げた。
「K氏、これを見てください。」
彼が指差すのは、朽ちたベッドサイドテーブル。
その上に、埃一つない、磨き上げられたように光るガラスコップが置かれていた。
K氏は手袋越しにコップを拾い上げた。
表面には、くっきりと指紋が残っている。
しかも、その指紋は湿り気を帯びているように見えた。
「まさか、誰かが最近までいたとでも?」
S助手はつぶやいた。
K氏は首を振る。
「このホテルの電気系統は完全に死んでいる。水道もだ。使用できるはずがない。」
彼はコップを元の場所に戻し、観察を続けた。
別の部屋では、ベッドのシーツが乱れ、枕には髪の毛のようなものが数本。
いずれも埃を被っておらず、ついさっきまで人が寝ていたかのようだった。
K氏は冷静にカメラを取り出し、写真を撮った。
最上階のスイートルームに辿り着いた時、夕日が窓から差し込んでいた。
部屋の中央にある豪華なテーブルには、古びた花瓶が乗っている。
その花瓶の周りには、奇妙なほど小さな水たまりができていた。
K氏が近づき、指で水たまりに触れた。
冷たい。
そして、彼の指が触れた瞬間、水たまりは微かに広がり、新しい指紋が鮮やかに浮かび上がった。
S助手は息を飲んだ。
「消えない…どころか、増えています!」
K氏は黙って、自分の指紋と、その水たまりの中で新たに生成されたような複数の水滴の跡を見つめた。
それはまるで、彼らの存在そのものが、このホテルの「記憶」に刻み込まれているかのようだった。
彼らが触れたもの、動かしたもの、呼吸した空気、そのすべてが、その瞬間から永遠に「消えない痕跡」として残る。
廃ホテルは、過去を留めるだけでなく、現在進行形の出来事を未来への「痕跡」として生成し続けていた。
K氏とS助手は、ホテルを後にした。
夕闇が完全にホテルを覆い隠す。
彼らの足跡は、ホテルの入口から内部へと、そしてまた外へと続く道に、鮮明に残された。
その時、彼らは気付かなかった。彼らが去った後も、ホテルの一室では、彼らの姿が半透明に浮かび上がり、その手は埃一つないコップを拾い上げ、水たまりに触れ、そして消えゆく姿が、永遠に再生され続けていることを。
ホテルの「消えない痕跡」とは、訪れた者の行動そのものの反復記録だったのだ。
#ショートショート#毎日投稿#AI#ホラー系#夕方
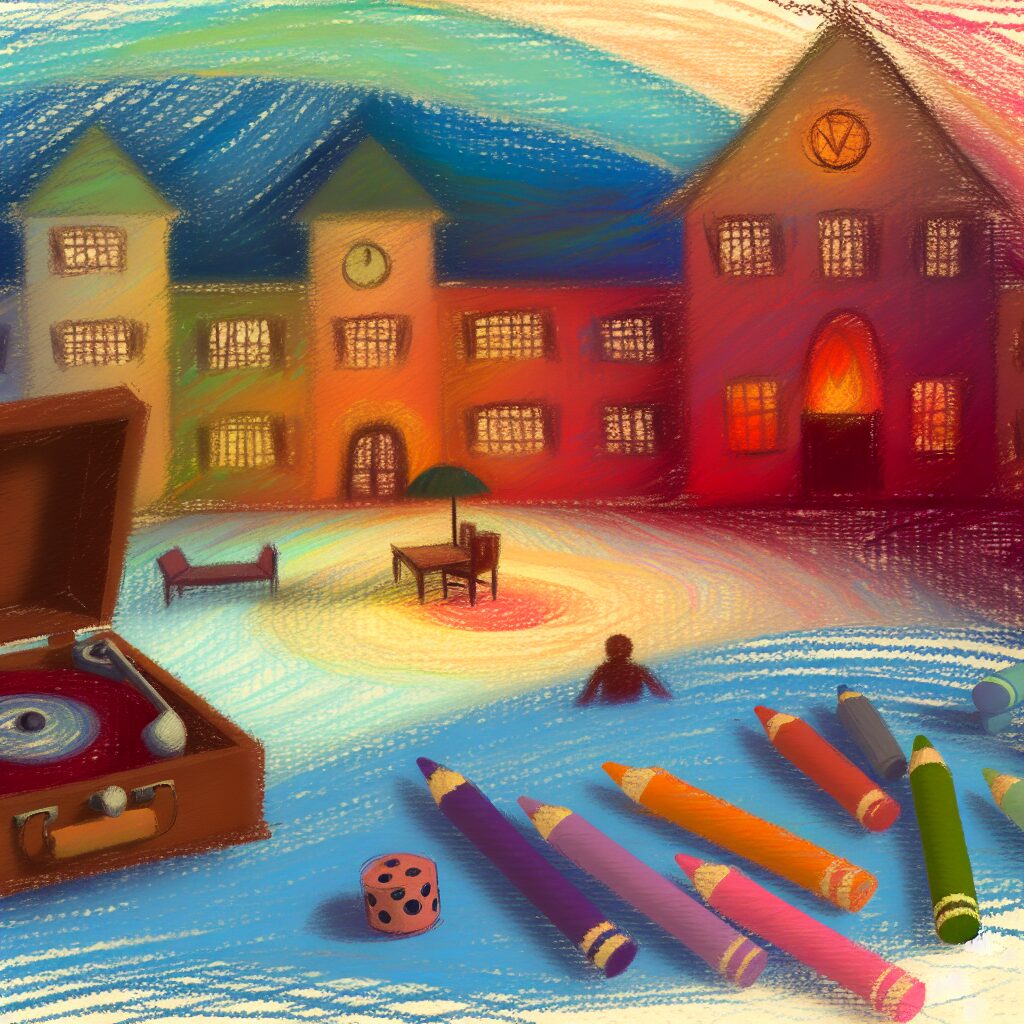

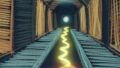
コメント