夕暮れの駅。
キノシタ氏はエスカレーターに乗った。
一日の疲れが肩にのしかかる。
群衆が彼を取り囲む。
誰もが皆、同じ方向を見ていた。
背後から、声が聞こえた。
「あれ、キノシタさんじゃないですか」
振り返るが、見知らぬ顔。
彼は会釈で返した。
気のせいか、と思った。
しかし、違う。
前方からも声がする。
「やあ、キノシタくん。この前の、例の件だけどね」
肩を叩かれた。
顔を見る。初めて見る男だ。
キノシタ氏は首を傾げた。
だが男は、まるで旧友のように親しげに微笑んだ。
エスカレーターが上昇するにつれて、異変は増した。
右からは、中年の女性が声をかけてきた。
「あら、奥さんお元気?この前のお茶会、楽しかったわね」
左からは、学生風の若者が手を振る。
「キノシタ先輩!課題、手伝ってくれてありがとうございました!」
皆、彼を、キノシタ氏を、知っている。
彼の名前を呼ぶ。
彼の過去の出来事について語る。
まるで彼の人生の、あらゆる場面に、彼らがいたかのように。
キノシタ氏は混乱した。
彼らの顔は、どれもこれも見覚えがない。
だが、彼らはあまりにも自然に、当然のように話しかけてくる。
一体これはどうしたことか。
夢でも見ているのか。
彼は必死に記憶を辿った。
しかし、彼らの顔はどれも、彼の記憶には存在しなかった。
汗が滲む。
エスカレーターの速度は一定だ。
ゆっくりと、彼は上昇していく。
しかし、彼の心臓は早鐘を打っていた。
周囲の会話が耳に飛び込んでくる。
「キノシタさん、そうそう、あの公園の桜、見事でしたね」
「先日は息子のことでお世話になりました」
「部長、今日の会議もすごかったですよ」
部長?公園の桜?息子?
キノシタ氏には、どれも覚えがない。
しかし、彼らは皆、笑顔で、親しげに彼に語りかける。
彼の目を見つめる。
そこには、純粋な親愛の情が宿っていた。
もはや、彼は無視することもできなかった。
彼らが、彼を、本当に知っているのだという事実が、重くのしかかった。
エスカレーターの終点が見えてきた。
彼は恐怖と安堵がないまぜになった息を吐いた。
この奇妙な状況から、早く抜け出したかった。
やがて、エスカレーターは終わりを告げた。
キノシタ氏は、人波に乗って地上に降り立った。
周囲を見回す。
先ほどまで彼に話しかけていた人々も、彼と一緒にエスカレーターを降りていた。
彼らはもう、キノシタ氏に話しかけない。
彼らはそれぞれの方向へ散っていく。
日常が戻ってきたかのように見えた。
キノシタ氏は深い息を吐いた。
悪夢のような時間だった。
彼は歩き出した。
その時、後ろから誰かが声をかけた。
「あの、すいません」
振り返ると、見知らぬ女性が立っていた。
キノシタ氏は身構えた。
だが、女性は困ったように微笑んだ。
「もしよかったら、そちらの方に道を教えていただけませんか。あそこの郵便局まで行きたいんですけど、確かキノシタさん、お詳しいですよね?」
キノシタ氏は一瞬、固まった。
そして、自然と口から言葉が出た。
「ああ、郵便局ですか。ええ、もちろん。この道をまっすぐ行って、二つ目の角を左ですね。そこを曲がると、すぐに見えてきますよ。あの、カミムラさん、お急ぎでしたら、私がそこまでご案内しましょうか?」
カミムラさん?
彼は今、見知らぬ女性を「カミムラさん」と呼び、まるで以前から知っているかのように道案内を申し出ていた。
そして、その「カミムラさん」も、彼に驚くことなく、ただ「ええ、助かりますわ」と微笑むだけだった。
キノシタ氏は、自分の口から出た言葉の意味を理解しようとした。
なぜ自分は、見知らぬ彼女を「カミムラさん」と呼んだのか。
なぜ、あの郵便局の道順を、知っているように話したのか。
彼は、自分が、彼らを、エスカレーター上の全ての人々を、知っていることに、静かに気づいた。
彼らの知らないうちに、エスカレーターは彼を、彼らの知る「キノシタ」にしていたのだ。
そして、彼は、彼らの人生の記憶を、いつの間にか共有していた。
#ショートショート#毎日投稿#AI#日常系#夕方
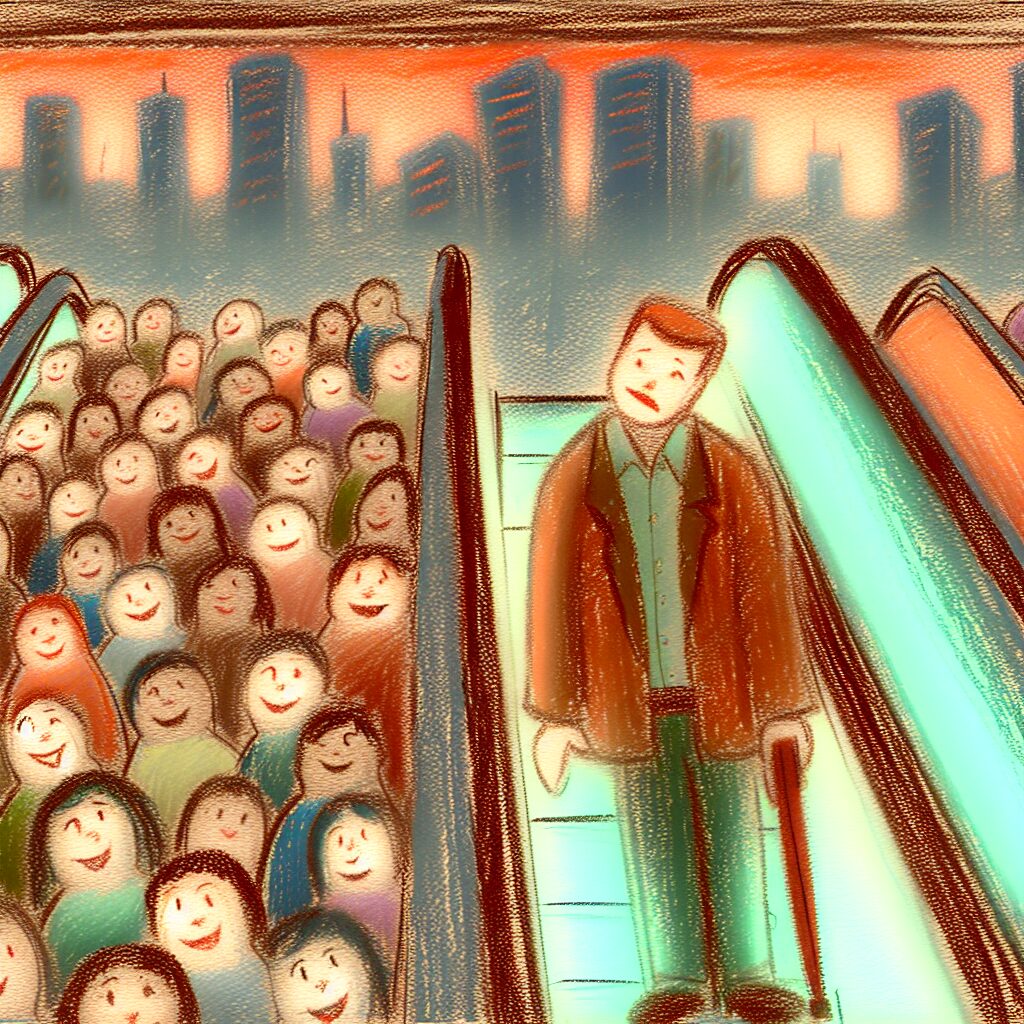


コメント